
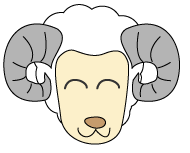

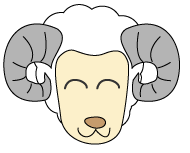

クロス屋さんにとって脚立は現場で作業する上で必要不可欠な道具の一つです。
特に戸建ての現場では階段や場合によっては吹き抜けなどがあるため様々な脚立の種類が必要になります。
この記事では主に戸建て住宅の現場で作業をするクロス屋さんが持っておくと便利な脚立を紹介していきます。
戸建てといっても注文住宅などの特殊な造りの現場もありますが、ここで紹介する脚立を持っていれば大抵の現場はなんとかなってしまう場合が多いです。
クロス屋さんは3尺の脚立をメインで使いますが、具体的にどのような脚立が必要になるのか見ていきましょう。
クロス屋さんの他の道具が気になる方はこちら 職人見習い君壁紙ってどうやって貼ってるの? クロス職人が様々な道具を駆使して貼っているんだよ勇助っ人 職人見習い君具体的にはどんな道具を使うの? クロス職人が使う道具を【メインの道具】【貼る道具】【パ ...

クロス屋さんの独立に必須な道具一覧!DIY壁紙貼替えにもおすすめ
Contents
クロス屋さんにおすすめの脚立3尺や5尺
脚立では尺という単位が使われますセンチに直すと約30センチだそうです。
まず下記の内容を説明していきます!
- クロス屋さんに3尺の脚立をおすすめする理由
- クロス屋さんが5尺の脚立を使う時
クロス屋さんに3尺の脚立をおすすめする理由
クロス屋さんでメインの脚立としてよく使われている3尺の脚立はセンチに直すと約90センチという事になりますね!
なぜクロス屋さんは3尺をメインの脚立として使うのかというと、一般的な家の天井の高さと相性が良いからです。
ちなみに脚立は基本天板に乗るように設計されていないので3尺の脚立の場合2段目に乗って作業する事が多いです。
日本の一般的な天井の高さは大体250センチぐらいなので3尺の脚立を使うと丁度良い高さで作業できるのです。
脚立の形状も様々な物があります。例えると脚立の踏ざん(踏み板の部分)の幅が広いものや狭いもの、天板に乗れるように天板が広く設計されているものなどがあります。
身長が高い人は2尺の天板に乗れるタイプの物を使用している人もいますが、天板に乗れるようなタイプの脚立だとしても天井を貼る時などに天板に足場板を掛けてしまうと監督さんに注意されてしまう事もあるので私は無難に3尺を使っています。
天板に乗れるタイプの3尺だと全体的に大きくなってしまい、道具を積む際などにかさばってしまうので、私は一般的なタイプの3尺の脚立を使っています。
あくまで自己責任にはなりますが、折り上げ天井など高い天井がある現場などは3尺の天板に足場板を掛けるしかない時もあるので使い勝手もいいです。(このような場合はいくら天板に乗れるタイプの脚立だとしても安全確認を怠らないようにしましょう!笑)
クロス屋さんが5尺の脚立を使う時
クロス屋さんは現場によって5尺の脚立を使う時があります。
具体的には天井が高い勾配天井やロフト付きの部屋やトップライトが付いている部屋などを作業する時に使われます。
3尺の脚立では届かない部分に使います。特にトップライトなどはハシゴなども掛けられないので5尺の脚立は必須です。
私は身長が178㎝あるので5尺の脚立があれば大抵はなんとかなってしまいますが、人によっては6尺の脚立をトップライト用にしても良いかと思います。
5尺の脚立は階段でも使い勝手がいいのでできれば5尺をおすすめします!
ちなみに6尺の脚立だと足の幅が広すぎて家によっては階段の幅に入らない場合もあります。そんな時は後に紹介する2連ハシゴを用意しておくと良いでしょう!
クロス屋さんにおすすめの伸縮足場板2選

クロス屋さんは天井や階段などを貼る時に伸縮の足場板を脚立に通して使います。
私の場合は長い伸縮足場板と短い伸縮足場板の2つを常備しいています。
具体的には
- 長い伸縮足場板:全長3.6m
- 短い伸縮足場板:全長2.7m
上記の長さの足場板を使い分けています。
長い伸縮足場板:全長3.6m
長い伸縮足場板は基本リビングなどの長い天井やテッウポウ階段などの縦長の階段などに使います。
リビングの場合だと稀に10mぐらいの天井を貼る場合もありますがそんな時も長い伸縮足場板と短い伸縮足場板、さらに立ち馬脚立まで持っていれば間違いないです。
長い伸縮足場板の場合天井の長さが4.5mぐらいまでなら貼れてしまいます。(天井の高さが2.5m以下で3尺の脚立に通した場合)
短い伸縮足場板:全長2.7m
短い足場伸縮足場板は天井の長さが3.6m以内の部屋や玄関、長さが短い階段などで使います。
天井の長さが3.6m以上でも脚立や立ち馬などを足してしまえば貼れってしまいます。
特に階段では長い伸縮足場板が入らない場合があるので短い伸縮足場板を持っておくと便利です。
もし仮に私がどちらか一つの足場板を選ぶとすれば短い伸縮足場板を選びます。
車に積むのにも便利ですし、長い伸縮足場板だと現場によっては使わない時も多いからです。
圧倒的に短い伸縮足場板の方が使用頻度は高いです。
しかし長い伸縮足場板が無いと話にならない現場などもあるので、普段は短い伸縮足場板を持ち歩き、必要に応じて長い足場板を持っていくのがベストだと思います。
クロス屋さんにおすすめの2連ハシゴ

2連ハシゴはハシゴが2つ重なって付いていてロープを引っ張る事で伸縮できるようになっているハシゴです。
主に階段や吹き抜けなどで使います。
私の場合はハシゴの足が伸縮できるようになっているタイプの2連ハシゴを使っていて、1Fから3Fの階段まですべてこの2連ハシゴを使っています。
壁に立てかける部分は壁紙が傷付かないように自作のカバーをしていて、3階建て戸建ての1Fから2F の階段のように段々が付いていて高さが低い階段でも重宝しています。
たまに酒箱を使っている職人さんもいますが私自身も以前酒箱で滑って危ない思いをしたので怪我のリスクを考えると2連ハシゴを使う事をおすすめします。
階段脚立のように4本の足をいちいち伸ばしたり縮めたりする必要がないのでかなり楽に貼れてしまい時短にもなっています。
2連ハシゴにも長い物や短い物がありますが、短くて足が伸縮できるようになっているタイプの2連ハシゴを持っておくとかなり便利だと思います。
クロス屋さんにおすすめの階段脚立
2連ハシゴの紹介で少し触れた階段脚立ですが、正直2連ハシゴを使っていれば出番は限られてくるでしょう!笑
それでも階段脚立がないと困ってしまう場合もあるので一応紹介しておきいます。
階段脚立とは、階段でも使えるように脚立の4本の足すべてが伸縮できるように設計されている脚立の事です。
どんな時に必要なのかというと、ズバリ階段の造りによって決まります。
言葉で説明すると難しいですが例えば3階建ての家でL字形の長めの階段を貼る場合、1Fから2Fの階段では2連ハシゴを掛ける場所が無いし2Fから3Fの階段ではL字形になっているので階段脚立がないと足場板を掛ける場所が無い時があります。
こんな時は階段脚立が無いと困ってしまいます。
私の場合は一応4尺の階段脚立を持っていますが3尺の階段脚立でも問題ないと思います。
なぜ私が4尺の階段脚立を持っているのかというと、単純に5尺を持っているので3尺だと足りなくて5尺だと高すぎる場合にも使えるからです。
何尺が良いのかはクロス屋さんによって違うと思いますが階段脚立は持っておくと便利な脚立のひとつです。
クロス屋さんにおすすめの伸縮立ち馬脚立

伸縮立ち馬脚立とは脚立と伸縮足場板を足して2で割ったような脚立です。
この脚立も4本の足すべてが伸縮できるようになっているタイプのものがあるので、ちょっとした折り上げ天井を貼る時に足を伸ばせば3尺の天板と同じ高さになるので便利だったりします。
洗面所を貼る時も立ち馬脚立を使えばトイレと同じように天井と壁の上場をすべて決めてから下場を貼ることができるので時短できます。
部屋やリビングを貼る時もわざわざ脚立を動かしたりしなくても壁の上場を一気に決めていく事ができるので使い方によってはかなり便利な使い方ができます。
私は特にリビングや部屋のパテを打ったり削ったりする時に重宝しています。
脚立を動かす頻度が圧倒的に減るので3尺の脚立を使うよりかなり速くパテが打ててしまいます。
クロス屋さんにおすすめの伸縮はしご(タケノコ)
伸縮ハシゴ、別名タケノコはその名の通りタケノコみたいな脚立です!笑
伸縮はしごは用途に合わせて一段一段伸縮できるハシゴで物によって違いますが全部で14段ぐらいあります。
14段のタイプの場合、縮長は1mぐらいで伸長は5.5mぐらいなので足場を組まないと届かないような吹き抜けの部分も届いてしまします。
どんな時に使うのかというと、足場が組めないほど狭い吹き抜けや、足場が外れてしまった後の是正やアフター工事の時に使います。
あまり使用頻度は高くないですが、持っていないとどうしようもない場合もあるので伸縮はしごは持っておくと便利なはしごの一つとして紹介しました。
クロス屋さんが持っていると便利な脚立まとめ

いろいろな脚立ははしごを紹介してきましたが最後にまとめてみるとこんな感じになりました!
- クロス屋さんに3尺の脚立をおすすめする理由
- クロス屋さんの脚立(5尺)
- クロス屋さんにおすすめの伸縮足場板2選
- クロス屋さんにおすすめの2連ハシゴ
- クロス屋さんにおすすめの階段脚立
- クロス屋さんにおすすめの伸縮立ち馬脚立
- クロス屋さんにおすすめの伸縮はしご(タケノコ)
ここで紹介したものはすべて私も持っていて実際に使っているものです。
全部持っていると間違いなく便利ですし作業をしていて困る事は無いと思いますが、脚立やはしごは身長によって使い方が違ってくると思うのであくまで参考程度にしていただければと思います。
私自身いろいろな脚立の使い方を試してきたのもあり、失敗もしてきてこの脚立編成にたどりついています!笑
同じクロス職人として脚立で悩んでいたり困っている職人さんのお役に立てる事が少しでもできたら嬉しいです。